「愛犬がてんかんと診断されてしまった。飼い主ができる対処法を知りたい」
「愛犬がてんかんと診断された飼い主さんの体験談を参考にしたい」
「今後の治療方針について具体的にどのようなことを話し合えばいいのか知りたい」
 りあ
りあはじめまして。
てんかんを患っている愛犬ちょちょと暮らして9年になる飼い主のりあです。



てんかん持ちだけど、主人がいろいろ勉強して対処してくれているおかげで、毎日元気いっぱいに過ごせているちょちょです。
「てんかん」はある日突然発症し、その後一生付き合っていかなければならない病気です。
私自身も愛犬が「てんかん」と診断されたとき、
(もう愛犬と一緒に過ごせる時間は長くないの?)
と悲しみと不安でいっぱいになりました。
しかし、私たち飼い主が適切なケアをしてあげることによって症状の軽減が期待できます。
この記事では、愛犬のてんかん歴9年の飼い主が、症状や対処法について体験談を交えながら解説します。
- 「てんかん」という病気と投薬の重要性について
- 「てんかん」の犬に対して飼い主ができること・やってはいけないこと
- 「てんかん」の治療方針について家族で話し合うことの重要性について
- 我が家の体験談
- 名前 ちょちょ
- 犬種 ダックスフンド
- 性別 メス
- 年齢 不明(老犬)
- 病名 てんかん
愛犬が初めて「てんかん発作」を起こした日
愛犬が我が家に来てから19日目の2014年12月19日。
それは、私が夕飯の支度を始めたときに突然起こりました。
ご飯を待ちきれず私の足元をうろうろしていた愛犬が、突然前のめりに倒れこみ、全身を硬直させながらぶるぶると震えだしてしまったのです。
- 最初は前脚のみ硬直し(前のめりに倒れた原因)、その後全身にけいれんが広がっていった
- 口は硬くなって開かない
- 目はカッと見開き、まばたきはできない状態
- てんかん発作は3分程で治まったが、前脚に麻痺が残り、10分程はふらつきながら歩いていた
- てんかん発作後は何も無かったかのように、ご飯を完食し、元気におもちゃで遊んでいた
犬がてんかん発作を起こしているときに絶対にやってはいけないこと
私は過去3匹のキャバリア犬を飼育していましたが、てんかんを患っていたコはいなかったため、病気に対して全く知識がありませんでした。
故に、てんかん発作を起こしている犬に対して絶対にやってはいけないことをやってしまいました。
- てんかん発作を起こしている犬の口内に手や指を入れる
- 犬の身体を揺する
≪てんかん発作を起こしている犬の口内に手や指を入れる≫
てんかん発作を起こしている犬は、自分自身を制御できない状態にあります。
てんかん発作を起こしている犬は力の制御ができないため、自身の口内に入ってきた飼い主さんの手や指をおもいっきり噛んでしまい、最悪指を噛みちぎられるという大怪我に繋がる危険性があるので絶対にやめましょう。
≪犬の身体を揺する≫
てんかん発作を起こしている犬は意識を失っているため、力任せに身体を揺すると怪我を負わせてしまう可能性があります。
また、てんかん発作を起こしているときに身体を揺すると、頭が強く揺れたり、首を捻ったりする可能性があり、脳に損傷を与える危険性が高まります。



主人はたまたま無事だったけれど、てんかん発作を起こしている犬の口に手や指を入れる行為はとても危険だから絶対にやらないように!
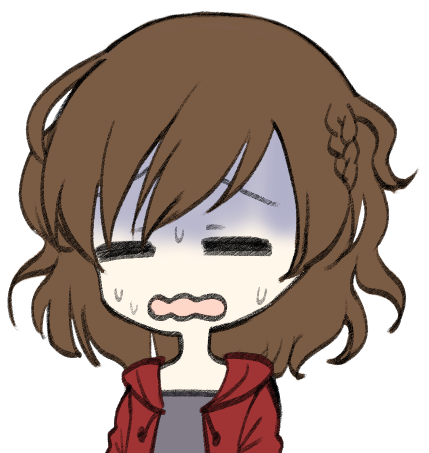
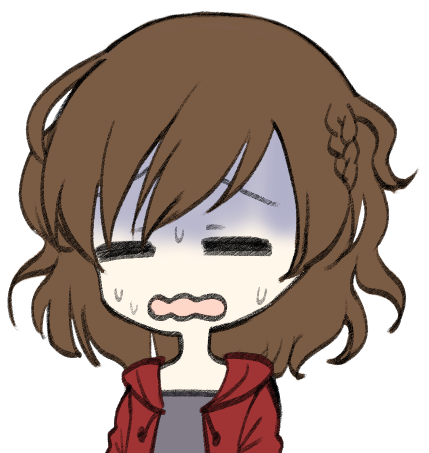
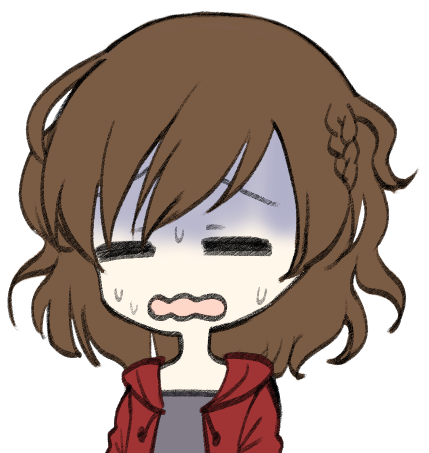
ごめんなさい…
(無知って恐ろしい…)
愛犬が「てんかん」の可能性有と診断されたときの私の心情
我が家の愛犬は迷子として保護した犬なのですが、この時点では所有権が前の飼い主にあったということもあり、最寄りの動物病院を全く調べていなかった私はかなり焦りました。
パニックになりながらも駅の近くに動物病院らしき建物があったことを思い出し、電話をかけて症状を伝えたところ、閉院間近であったにもかかわらず「犬が落ち着いてからでいいので連れてきてください」と仰っていただけたので、愛犬が落ち着きを取り戻した30分後に動物病院へ向かいました。
内診の結果、
- 直近で頭部に外傷を負うような事故にはあっていない
- 頭部が膨らんでいるなど見た目に変化が無い
- 保護されてから日が浅い
- 初めてけいれんを起こした
ということから、
「てんかん」の可能性有。要経過観察。
という診断が下りました。



「てんかん」の可能性有?
「てんかん」は「けいれん」を起こす病気じゃないの?



一度「けいれん」を起こしただけでは「てんかん」とは診断されないんだよ。
詳しくは下の記事で解説していますので、良かったら読んでみてください。


この日、私は初めて犬にも「てんかん」という病気があることを知り、愛犬がその病気を患っているかもしれないという不安でいっぱいになりました。
ですが、確定診断では無かったことと、我が家の愛犬がそんな大病を患っているなんて信じたくない!という否定したい気持ちから、病気と向き合う覚悟を持てずにいました。
愛犬が「てんかん」と診断された日
三ヶ月の保護期間が終了し、正式に我が家の犬として迎え入れてから暫くはてんかん発作が起きることは無く、平和な日々を過ごしていました。
ですがこの病気は突然やってきます。
2015年10月11日
私の足元で昼寝をしていた愛犬が突然飛び起き、再びけいれんを起こしました。
- あっという間に全身にけいれんが広がる
- 口は硬くなって開かない
- 目はカッと見開き、まばたきはできない状態
- てんかん発作は3分程で治まったが、5分程はふらつきながら歩いていた
- てんかん発作後は何も無かったかのように、再び昼寝を始めた
この日は動物病院が休診日でしたが、最初にてんかん発作を起こした日から少しずつ「犬のてんかん」について勉強し始めていた私は、多少知識がついたこともあり、冷静に対処することができました。
てんかん発作を起こした犬を興奮させないようにするポイント6つ
- てんかん発作を起こした当日と翌日の散歩は控える
- 不安やストレスを溜めないように、いつも以上にコミュニケーションやスキンシップをはかる
- 突然叫んだり、大きな音をだしたりしないよう気をつける
- 家族がいる場合、喧嘩しないよう気をつける
- 家族がいる場合、帰宅時にチャイムを鳴らさないよう前もって連絡をしておく
- 可能ならばチャイムの電源をOFFにしておく



スキンシップは、綱引きやキャッチボールなどのアクティブな遊びは避けましょう。
マッサージや抱っこなど、ソフトなスキンシップを沢山してあげてね☆
愛犬が「てんかん」と診断されたときの私の心情
翌日、仕事から帰宅した私はすぐに愛犬を動物病院へ連れて行き、昨日起きたてんかん発作の症状を獣医師に伝えました。
内診の結果、
- 前回の発作から半年以上経過しており、直近で受けた健康診断の結果も良好だったことから「特発性てんかん」と診断される
- てんかん発作が起こる間隔が長いため、現時点での投薬治療は必要無い
と、獣医師から説明を受けました。
この日、ついに「てんかん」という診断が下りました。
初めて「てんかんの可能性がある」と言われた日から約半年。
信じたくない
嘘であってほしい
と、否定的な気持ちを持ちつつも、万が一「てんかん」だった場合、すぐに適切なケアをしてあげられるように知識はつけておこうと勉強してきた私は、自分が思っていたよりも冷静に診断を受け入れることができました。



ショックだったことに変わりはありませんが、勉強して、それなりに知識もついてきていた頃だったので、「愛犬を失うかもしれない」という恐怖心はありませんでした。
愛犬が投薬治療の対象と診断された日
2015年10月20日
前回のてんかん発作から数日後のことでした。
コングで遊んでいた愛犬が、突然もの凄い勢いで走り出したかと思うと、そのまま腰が抜けたように崩れ落ち、あっという間に全身にけいれんが広がり倒れてしまいました。
このとき初めて、ひと月の間にけいれんが2回起きました。
- 突然腰が抜けたように後ろ脚に力が入らなくなり、全身にけいれんが広がる
- 口は硬くなって開かない
- まばたきはしていたが、涙がボロボロとこぼれ落ちていた
- てんかん発作は2分程で治まったが、5分程はふらつきながら歩いていた
- てんかん発作後は何も無かったかのように、再びコングで遊び始めた
愛犬が「投薬治療の対象」と診断されたときの私の心情
この日は私が休みだったため、すぐに動物病院へ駆け込むことができました。
内診の結果、
- 前回から10日程で発作が起こってしまったため、投薬治療の対象になる
- 動画の映像と発作前後の様子から、てんかん発作のなかでは軽いほうと診断される
と、獣医師から説明を受けました。
「投薬治療の対象」
私はこの言葉に、愛犬に初めて「てんかん」の可能性があると診断されたときと同じくらいのショックを受けました。
抗てんかん薬を飲ませるということは、
- 一度、抗てんかん薬を飲み始めると一生飲み続けなければならないこと
- 肝機能障害等別の病気になる可能性があること
を覚悟しなければならないからです。
まだ(おそらく)若いのに、愛犬を一生薬漬けにするなんて…
抗てんかん薬を飲ませたせいで、肝機能障害にさせてしまったら…
いろいろな不安や恐怖心が頭の中をぐるぐると回り、その日はすぐに返事をすることができませんでした。
「てんかん」は進行性の脳の病気ということを知っていますか?
帰宅後、抗てんかん薬を「飲ませるか」「飲ませないか」を決断するため、もっと「てんかん」という病気について知る必要があると考えた私は、ネットで情報を漁りました。
そうして調べていくうちに「てんかん」という病気の本質にたどり着きました。
- てんかんの発作は進行性である
- てんかんの発作は進行が進むにつれ、抗てんかん薬が効かなくなっていく
言葉で説明されてもいまいちピンと来ないかと思い、イラストにしてみました。


上のイラストのように、てんかんは発作を繰り返すたびに脳が損傷していきます。
そのため、発作の頻度はどんどん増え、最初は数分間けいれんを起こすだけだった発作が、やがて命の危険を伴う重積発作を引き起こすようになります。
現在、抗てんかん薬には様々なものがありますが、重積発作を伴う難治性てんかんに効く抗てんかん薬は多くはありません。
抗てんかん薬への不安:薬を飲ませたくない飼い主の心情
私もそうでしたが、ある日突然獣医師から、
「抗てんかん薬を服用して治療したほうがいい」
と言われても、
「はい分かりました」
と、すんなり受け入れられる飼い主さんは少ないと思います。
ある程度「てんかん」についての知識を持っている飼い主さんとしては、
- 一度、抗てんかん薬を飲み始めると一生飲み続けなければならないこと
- 肝機能障害等別の病気になる可能性があること
を不安に思うことは当然です。
上のイラストで示した事実を理解したうえで、愛犬への投薬治療をいつから始めるのかを決めるのは、獣医師ではなく飼い主さん自身であるということをまずは覚えておいてください。
愛犬の今後の犬生が自身の決断によって命がかかわるほど大きく左右される
これは私達が想像する以上に心身の負担となりますし、とても大事なことなので家族がいる場合は相談する必要もあります。
だから抗てんかん薬による治療の話が出ても、その日・その場ですぐに決断しなくても大丈夫です。
犬の状態によっては、話し合いにあまり時間をかけることができない場合もありますが、私個人の意見としては、飼い主さん自身が「理解」「納得」「覚悟」ができていない状態で投薬治療を始めるのはおすすめできません。
病気に限った話ではありませんが、自分の頭でしっかり考え、納得してから行動に移すようにしないと、何かあったときに他人のせいにしたり、必要以上に自分を責めてしまうことになりかねません。
まずは一旦話を持ち帰り、しっかり勉強して、家族と話し合って、治療に対する「理解」「納得」「覚悟」が出来てから投薬治療を始めましょう。
愛犬の「てんかん」の治療方針について家族で話し合おう
家族がいる場合、今後の治療方針について話し合うことは重要です。
話し合いをすることにより、家族全員が飼い主であるという自覚を持ってもらい、「てんかん」という病気について理解を深めることで、今後の治療をスムーズに進めることができます。
また、命にかかわる決断故、飼い主にかかる心理的負担を分散させるという効果もあります。



ここからは、我が家の家族会議で決めた治療方針を交えながら、具体的にどういったことを話し合えばいいのかをご紹介させていただきます。
「てんかん」の検査をするか・しないか
犬の「てんかん」の確定診断をするためには以下の検査が必要になります。
- 身体検査
- 神経学的検査
- 画像診断
- 血液検査
- 心臓検査
- MRI検査
- 脳脊髄液検査
犬の「てんかん」の確定診断には、MRI検査・脳脊髄液検査の結果によって初めて確定診断が下ります。
とはいえ、MRI検査や脳脊髄液検査ができる病院は限られるうえ、検査費用も10万円前後かかります。
さらに、基礎疾患がある犬や老犬には麻酔のリスクもあります。



話し合いの結果、我が家では「てんかん」の検査は受けないことにしました。
- 外傷を疑うような出来事が無かった
- 腫瘍を疑うような症状は無い
- 獣医師より既にてんかん発作の中では軽いほうと診断されている
- 持病があるため身体にかかる負担とリスクが高すぎる
- 費用対効果が悪い(費用・通院・異常が見つからないケースもある等)
抗てんかん薬を飲ませるか・飲ませないか



話し合いの結果、我が家では抗てんかん薬による治療は暫く見送ることにしました。
- 獣医師よりてんかん発作の中では軽いほうと診断されている
- 今回たまたまひと月に2回てんかん発作が起きただけの可能性もある
抗てんかんを飲ませない場合、どのタイミングで投薬治療を開始するか
抗てんかん薬による治療を見送る場合、愛犬がどういう状態になったら投薬治療を開始するのかも話し合っておけば、今後スムーズに治療を開始できます。



話し合いの結果、我が家では愛犬が以下のような状態になったら投薬治療を開始することに決めました。
- 重積発作を起こしたとき
- ひと月の間に3回以上てんかん発作を起こしたとき
- 一日に2回以上てんかん発作を起こしたとき
話し合いの際、これらの要点を家族で話し合っておくことをおすすめします。
愛犬が抗てんかん薬による治療を開始するまで
その後、我が家の愛犬は、幸いにも暫くてんかん発作を起こすことは無く、4回目は約半年後の2016年3月31日、5回目は2016年8月12日といった感じで、半年から季節の変わり目の時期に軽いてんかん発作を起こすという状態が2021年6月まで続きました。
2021年7月。
引っ越しをきっかけに、てんかん発作が一ヶ月に1回の頻度で起こるようになってしまいます。
獣医師に相談したところ、ミダゾラム鼻腔噴霧液という坐薬を勧められました。
投与してみたところ愛犬にはよく効いたため、そのまま様子を見ることとなります。
2022年5月。
とうとうひと月の間に3回以上てんかん発作を起こしたため、抗てんかん薬による治療を開始することになりました。
我が家は、ゾニサミド系のエピレス錠を選択し、投薬治療を続けています。



抗てんかん薬の種類や副作用、効果についてはこちらの記事で詳しく解説していますので、良かったら読んでみてください。




まとめ:「てんかん」を正しく理解し治療方針を家族で話し合おう
ここまで我が家の体験談を交えながら、犬の「てんかん」について解説をしてきました。
犬の状態は勿論のこと、各家庭で考え方や事情は異なります。
大切なのは「てんかん」という病気を正しく理解し、家族できちんと話し合って治療方針を決めるということです。
その話し合いの際に、我が家で決めたことが少しでも参考になれば幸いです。
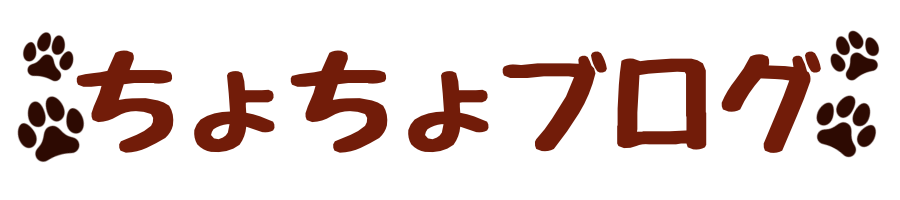

コメント